【企業経営者必読】SSBJによるサステナビリティ開示基準策定の最前線:スコープ3義務化が迫る中、企業が今すべきこと
はじめに:サステナビリティ開示が「任意」から「必須」へ
近年、地球温暖化の進行や社会課題への関心の高まりを背景に、企業の財務情報だけでなく、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)といった非財務情報、特にサステナビリティに関する情報開示の重要性が国際的に急速に高まっています。世界の投資家や金融機関は、企業の持続可能性への取り組みを投資判断においてますます重視するようになっており、信頼性のある情報開示が求められています。
こうした国際的な潮流を受け、日本国内においても、企業がサステナビリティに関する情報をどのように開示すべきかという「国内基準」の策定が喫緊の課題となっていました。この重要な役割を担うのが、2022年7月に設立された**SSBJ(サステナビリティ基準委員会:Sustainability Standards Board of Japan)**です。
SSBJは、国際的な開示基準であるISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が開発した基準(IFRSサステナビリティ開示基準)との整合性を図りつつ、日本企業の法規制や実情を踏まえた国内基準の策定を進めています。そして、2024年3月には、気候関連開示に関する国内基準の「公開草案」が公表され、サステナビリティ開示が「任意」から「必須」へと大きく舵を切る具体的な道筋が示されました。
本コラムでは、このSSBJが策定を進める国内基準の最新動向、特に多くの企業に影響を与えるスコープ3の開示義務化を含む主要な要求事項、そして基準適用に向けたロードマップについて詳しく解説します。これは、上場・非上場を問わず、すべての企業が今後直面する可能性のある重要な変化であり、早期の理解と準備が求められます。プロのビジネスライター/ブロガーの視点から、この変化が企業経営に与える影響と、企業が今すぐ取り組むべき事項についても深掘りしていきます。
SSBJ設立の背景と国内基準策定の重要性
ISSB基準との整合性と「日本企業の実情」の調和
SSBJが設立された背景には、サステナビリティ情報の開示に関する国際的な議論の加速があります。G20やG7といった主要な国際会議においても、企業のサステナビリティ情報開示の重要性が繰り返し確認され、そのグローバルなベースラインとしてISSB基準の策定が強く推進されてきました。
ISSBは、財務報告の国際基準であるIFRS基準を策定するIFRS財団のもとに設置され、2023年6月には気候関連開示基準(IFRS S2)を含む包括的なサステナビリティ開示基準(IFRS S1)を公表しました。これらの国際基準は、各国の規制当局や基準設定主体が国内の開示基準を策定する際の強力な参照点となることが期待されています。
SSBJは、このような国際的な動きと歩調を合わせる形で設立されました。SSBJの設立目的は明確であり、それは**「ISSB基準との高い整合性を図りながら、日本企業の法規制や開示実務、経済情勢なども考慮に入れた、企業のサステナビリティ開示に関する国内基準を開発・策定すること」**です(出典:SSBJウェブサイト『SSBJについて』等)。これは、日本の企業が国際的な開示基準に基づき情報を開示できるようにすることで、海外を含む投資家からの信頼性を高め、国際的な比較可能性を確保すると同時に、国内の多様な企業の状況にも配慮した現実的な基準とすることを目指すものです。
SSBJの委員は、提供いただいた情報にあるように、日本の会計基準を設定する企業会計基準委員会(ASBJ)の委員長である川西安喜氏が委員長を務め、会計、環境、金融、法律など多様な分野の専門家13名で構成されています(参照:SSBJウェブサイト 委員構成)。この構成は、単なる会計基準の延長としてではなく、サステナビリティという広範なテーマに対して専門的かつ多角的な視点を取り入れる姿勢を示しています。
SSBJは、2024年3月に、気候関連開示に関する国内基準の公開草案を公表しました。この草案は、ISSBのIFRS S2をベースとしつつ、日本の開示制度(例:金融商品取引法に基づく有価証券報告書など)や企業の実務を踏まえた修正や加筆が行われたものです。この公開草案に対する意見募集(パブリックコメント)を経て、正式な国内基準が確定されるプロセスが進められています。
SSBJ公開草案の核心:企業に求められる主要な開示要求事項
スコープ3の義務化、シナリオ分析、そして財務情報との連携
2024年3月に公表されたSSBJの気候関連開示に関する公開草案は、今後の企業の情報開示に大きな影響を与える重要な内容を含んでいます。提供いただいた情報に基づき、その主要な要求事項を深掘りします。
-
温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)の開示義務化:
- 「草案では企業の温暖化ガス排出量であるスコープ1、2に加え、原材料の調達や製造などのスコープ3の開示も求めた。」 スコープ1は自社の事業活動における燃料の燃焼などによる直接排出、スコープ2は自社が購入した電力や熱などのエネルギー起源の間接排出です。これらは既に一部の大企業などが算定・開示していますが、SSBJ基準の下ではその算定方法や開示形式が標準化されます。
- 特筆すべきはスコープ3の開示が求められている点です。スコープ3は、自社のバリューチェーンにおける上流(例:原材料の調達・輸送)から下流(例:販売した製品の使用・廃棄)に至るまで、自社以外の主体からの間接排出を15のカテゴリーに分類して算定するものであり(参照:環境省『サプライチェーン排出量算定の考え方』)、多くの企業において排出量全体の大部分を占めます。スコープ3の算定は、データの入手や計算の複雑さから中小企業を含む多くの企業にとって大きな負担となります。しかし、サプライチェーン全体での排出量削減(GX)には不可欠な情報であり、SSBJ基準ではこの開示が必須となります。
-
気候関連のリスクおよび機会に関する財務情報の開示:
- 公開草案は、気候変動が企業の財政状態、経営成績、キャッシュフローに与える(または与える可能性のある)影響に関する情報の開示を求めています。提供いただいた情報にあるように、「気候関連のリスクに対応するための投資額や、社内炭素価格の公表なども盛り込んだ。」 これは、気候変動がもたらす物理的リスク(例:異常気象による設備損壊、水資源不足)や移行リスク(例:炭素価格の上昇、市場の変化による座礁資産化)に対して、企業がどのような投資を行い、財務的にどのように備えているかを示すものです。また、「社内炭素価格」(Internal Carbon Price: ICP)は、企業が内部的に設定する炭素排出量あたりの価格であり、投資判断や事業計画に脱炭素の視点を組み込むための指標です。その公表は、企業の脱炭素への真剣度を示す指標となります。
-
シナリオ分析の実施と開示:
- 気候変動が事業に与える影響は不確実性が高いため、SSBJ草案では、提供いただいた情報にあるように、「気候変動で起こりうる事業上のリスクや機会を評価する「シナリオ分析」も求めている。」 シナリオ分析では、例えば「世界の平均気温が1.5℃上昇した場合」「2℃上昇した場合」「4℃上昇した場合」といった複数の気候変動シナリオの下で、自社の事業モデルがどのような物理的リスク(例:「例えば、世界の平均気温が2度上昇した場合に自社の生産拠点が水没するなどのリスクを想定し、対策を示すといった内容だ。」)や移行リスクに直面する可能性があるかを評価し、それに対する企業の戦略やレジリエンス(強靭性)を示すことが求められます。これは、単なるリスクの列挙ではなく、将来的な気候変動の影響を見据えた企業の経営戦略やリスク管理体制の有効性を投資家に説明するための重要なツールとなります。
これらの要求事項は、企業に対し、気候変動を経営の根幹に関わる課題として捉え、リスク管理、事業戦略、財務計画と一体的に検討し、その内容を透明性高く開示することを求めるものです。
義務化へのロードマップ:段階的な適用と金融庁の役割
SSBJが策定した国内基準は、ISSB基準と同様に、上場企業を中心に段階的に適用されていく見込みです。提供いただいた情報には、SSBJが検討している具体的な適用時期と範囲案が示されています。
- 「基準の適用時期や範囲については、時価総額に合わせて段階的に義務化する案が検討されている。」 これは、全ての企業に一度に適用するのではなく、影響力の大きい企業から順に義務化を進めるという現実的なアプローチです。
- 「すべての企業を対象に26年3月期に任意適用をスタートさせ、時価総額3兆円以上の企業は27年3期から開示を義務化する流れだ。」 これは、SSBJが公開草案で示した具体的なロードマップ案です。2026年3月期から任意での適用を開始し、まずは投資家への影響力が大きい時価総額3兆円以上の大企業から、2027年3月期より開示が義務化されるという流れが想定されています。その後、段階的に時価総額が小さい企業にも義務化の対象が拡大していく可能性があります。
このロードマップ案は、SSBJの公開草案段階のものであり、パブリックコメントの結果や今後の議論によって修正される可能性はあります。しかし、サステナビリティ開示が義務化されるという方向性は揺るぎなく、その時期が刻一刻と近づいていることを示しています。
SSBJが策定した基準案が正式に導入されるためには、「SSBJが決めた基準案は、金融庁が最終的に適用を決める手続きを経て、正式に導入される。」 というプロセスを経る必要があります(出典:金融庁ウェブサイト 企業開示に関する情報等)。金融庁は、企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正を通じて、SSBJ基準を日本の開示制度に組み込む最終的な判断を行います。したがって、SSBJの議論の行方と並行して、金融庁の動向も注視する必要があります。
SSBJ基準適用が企業に与える影響:準備状況が問われる時代へ
SSBJが策定するサステナビリティ開示基準の適用は、企業経営に多方面から影響を与えます。特に、これまでサステナビリティ情報開示に積極的ではなかった企業にとっては、大きな負担となる可能性があります。
- 開示体制の構築とデータ収集・管理の課題: スコープ1, 2に加え、特にスコープ3の排出量を正確に算定し、継続的に管理するためには、社内の体制構築や、サプライヤーを含むバリューチェーン全体からのデータ収集協力が不可欠となります。これは、多くの中小企業を含むサプライヤー側にも、排出量算定・開示能力が求められるようになることを意味します。
- 専門知識・人材育成の必要性: 気候関連リスク・機会の評価、シナリオ分析の実施、社内炭素価格の設定、そしてこれらを適切に開示するためには、環境、財務、戦略といった複合的な専門知識が必要です。社内での人材育成や外部専門家(環境コンサルタント、脱炭素アドバイザーなど)との連携強化が求められます。政府が推進する「リスキリング」支援制度なども、こうした人材育成に活用できる可能性があります(参照:厚生労働省『人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)』)。
- コストとリソースの確保: 新たな情報開示体制の構築、データ収集システムへの投資、専門家の活用、従業員研修などには、一定のコストとリソースが必要となります。特に中小企業にとっては、これが大きな負担となる可能性があります。
- 経営戦略との一体化: サステナビリティ開示は、単なる報告業務ではなく、企業の気候変動に対するリスク認識、戦略、ガバナンスを示すものです。これを機会に、サステナビリティ(特に脱炭素)を経営戦略の根幹に組み込み、事業活動と一体で推進していくことが求められます。形式的な開示では、投資家やステークホルダーからの評価は得られません。
SSBJ基準がもたらす課題と機会:変革を成長の糧に
SSBJ基準の導入は、企業にとって避けられない「課題」であると同時に、新たな「機会」でもあります。
【主な課題】
- スコープ3算定の複雑さとデータ収集の難しさ: バリューチェーン全体にわたるデータの収集・集計は、特に多くのサプライヤーを持つ企業にとって大きな課題です。中小サプライヤーの協力体制構築が不可欠となります。
- シナリオ分析の技術的なハードル: 複数の気候シナリオに基づき、事業への影響を定量的に評価するには専門的な知識とツールが必要です。
- 開示準備にかかる時間とコスト: 体制構築、データ収集、分析、報告書作成など、基準に準拠した開示を行うには 상당(サンタン:相当)な時間とコストがかかります。
【掴むべき機会】
- 投資家からの評価向上と資金調達の円滑化: 高品質なサステナビリティ開示は、ESG投資家からの評価を高め、株式価値向上やサステナビリティ関連融資などの資金調達機会の拡大に繋がります。
- 企業イメージ・ブランド価値の向上: 透明性の高い情報開示は、企業の信頼性を高め、消費者、従業員、地域社会からの支持獲得に貢献します。
- リスク管理能力の強化: シナリオ分析等を通じて、気候変動が事業に与えるリスクを早期に特定し、対策を講じることで、事業のレジリエンス(強靭性)を高めることができます。
- 新たなビジネス機会の発見とイノベーション促進: バリューチェーン全体の排出量削減に取り組む過程で、新たな省エネ技術、低排出量な製品・サービスの開発、サプライヤーとの協業機会などが生まれます。これはGXによる経済成長にも繋がります。
- 社内コミュニケーションの活性化と人材確保: サステナビリティ目標を共有し、開示に向けて部門横断的に協力することで、社内のコミュニケーションが活性化し、従業員のエンゲージメント向上に繋がります。環境意識の高い人材にとって、透明性の高いサステナビリティ情報を開示している企業は魅力的な選択肢となります。
今後の展望と企業への要請:準備は今すぐ!
SSBJによる国内基準策定のプロセスは最終段階に近づいており、金融庁による正式な適用決定を経て、早ければ2027年3月期には一部の大企業で開示が義務化される見込みです。その後、義務化の対象は段階的に拡大していく可能性が高く、今は対象外の中堅・中小企業にとっても、主要な取引先からスコープ3開示への協力が求められるなど、無関係ではいられなくなります。
企業は、この変化を単なる「規制対応」として受け身で捉えるのではなく、自社の経営戦略や企業価値向上に繋がる「機会」として積極的に捉えることが重要です。
今すぐ取り組むべきこととして、まずはSSBJや金融庁のウェブサイトで最新の情報を確認し、公開草案の内容を把握することから始めましょう。そして、自社の温室効果ガス排出量(特にスコープ1, 2)の算定を開始し、スコープ3についても、可能な範囲でデータの収集や算定方法の検討を進めることが推奨されます。専門知識が不足している場合は、政府や自治体が提供する相談窓口や専門家派遣制度、リスキリング支援などを積極的に活用しましょう。
サステナビリティ開示の義務化は、企業が社会からの信頼を得て、持続的に成長していくための新たなスタートラインです。早期に準備を始め、高品質な情報開示を通じて、企業価値の向上と未来への競争力強化を実現しましょう。
エビデンス・主な情報取得元
- SSBJ(サステナビリティ基準委員会)ウェブサイト: https://www.ssbj.jp/ (SSBJの概要、活動状況、公開草案などの一次情報)
- 金融庁ウェブサイト: https://www.fsa.go.jp/ (企業開示、サステナビリティ関連政策、SSBJ基準の適用決定プロセスに関する情報)
- 経済産業省ウェブサイト(特にGX関連、資源エネルギー庁など): https://www.meti.go.jp/ (GX戦略、投資促進策、省エネ関連補助金、グリーン・バリューチェーン関連情報)
- 環境省ウェブサイト: https://www.env.go.jp/ (カーボンニュートラル目標、排出量算定ガイドライン、地域脱炭素、脱炭素ポータル関連情報)
- 中小企業庁ウェブサイト: https://www.chusho.meti.go.jp/ (中小企業政策全般、ものづくり補助金、IT導入補助金、事業継続力強化計画(BCP)関連情報)
- 厚生労働省ウェブサイト: https://www.mhlw.go.jp/ (人材開発支援助成金(リスキリング)関連情報)
- ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)ウェブサイト: https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/ (ISSB基準(IFRS S1, S2)の原文など、国際動向に関する情報)
※本コラムで引用した情報や日付(例:2024年3月の公開草案、2026年3月期・2027年3月期の適用案など)は、公開時点の情報に基づいています。正式な基準や適用時期は、今後の政府、SSBJ、金融庁等の決定により変更される可能性があります。必ず最新の公式情報をご確認ください。



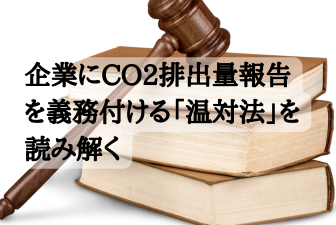
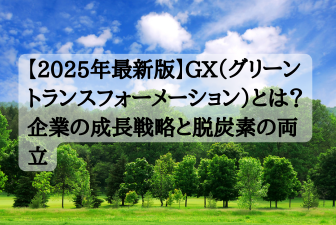





この記事へのコメントはありません。