【脱炭素の基盤】企業にCO2排出量報告を義務付ける「温対法」を読み解く:カーボンニュートラル実現への礎
はじめに:日本の温暖化対策を支える「礎石」
気候変動への対応が世界的な最重要課題となる中、各国は温室効果ガス(GHG)排出量削減に向けた様々な法規制や政策を導入しています。日本においても、この温暖化対策の根幹をなす法律として、「地球温暖化対策の推進に関する法律」、通称「温対法(おんたいほう)」が存在します。
温対法は、「日本の政府や自治体、企業による温暖化対策の土台となる法律で、正式名称は地球温暖化対策の推進に関する法律。」 です。
この法律に基づき、日本全体としてのGHG排出量を削減し、「GHG排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラル社会を目指した総合的な温暖化対策づくりが進められている。」 のです。
単に目標を掲げるだけでなく、その達成に向けた具体的な仕組みを定める温対法は、日本の温暖化対策において欠かせない存在です。特に、特定の事業者に対して温室効果ガス排出量の報告を義務付けている点は、企業が自らの排出量を認識し、削減に向けた第一歩を踏み出す上で非常に重要な役割を果たしています。
本コラムでは、温対法の成り立ちから基本理念、そして企業に課される具体的な義務である排出量報告制度を中心に、その意義と役割を詳しく解説します。
また、現代の日本の脱炭素・GX化戦略において、温対法がどのように位置づけられ、企業がどのように対応すべきかについても深掘りしていきます。
温対法の誕生とその歴史:国際合意との連動
京都議定書が引き金となった日本の第一歩
温対法は、国際的な気候変動対策の枠組みと密接に連動して生まれました。その成立の大きな契機となったのは、1997年に京都で開催された「第3回気候変動枠組み条約締約国会議(COP3)」です。
この会議では、「先進国にGHG排出削減を義務付ける京都議定書が採択された。」
国際的な排出削減義務を負うことになった日本は、国内での対策を法的に担保する必要に迫られました。これを受け、「日本政府は温暖化対策の第一歩として、98年に温対法を成立させた。」 (出典:環境省ウェブサイト『地球温暖化対策推進法』沿革等)。温対法は、京都議定書の目標達成に向けた国内措置を推進するための法的な基盤として位置づけられたのです。
その後、国際的な枠組みは京都議定書から、より包括的で全ての国が参加するパリ協定へと移行しました(2015年採択、2016年発効)。パリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて1.5度以内に抑える」という長期目標が設定されました。日本の温対法も、この新たな国際合意に合わせて改正が重ねられ、その基本理念として、「世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて1.5度以内に収めるとするパリ協定の目標と、2050年カーボンニュートラルの実現を基本理念として掲げている。」 と明確に位置づけられています(出典:環境省『地球温暖化対策推進法』条文)。
温対法は、GHG排出削減という目標に向かう日本の取り組みが、常に最新の科学的知見や国際的な潮流と整合していることを示す、進化し続ける法律と言えます。
温対法が対象とするGHG:管理すべき「温暖化ガス」の種類
CO2だけではない!包括的なGHGリスト
「温暖化ガス」というと、多くの方がまず二酸化炭素(CO2)を思い浮かべるでしょう。CO2は確かに最大の排出量を持つGHGですが、温対法が対象とするGHGはCO2だけではありません。
「温暖化ガス(GHG)の種類を二酸化炭素(CO2)やメタンなどと定め、同法に基づいて…」 さらに、「温対法では一酸化二窒素やハイドロフルオロカーボン類なども日本全体で管理すべき具体的なGHGの対象に挙げた。」
具体的には、温対法は以下の7種類の温室効果ガスを地球温暖化の原因となる物質として指定し、その排出量の把握と削減を管理しています(出典:環境省ウェブサイト『地球温暖化対策推進法』関連情報)。
- 二酸化炭素(CO2): 化石燃料の燃焼などが主な発生源。
- メタン(CH4): 天然ガスの生産・輸送、農業(畜産、水田)、廃棄物の分解などが主な発生源。
- 一酸化二窒素(N2O): 燃料の燃焼、工業プロセス、農業(肥料の使用)などが主な発生源。
- ハイドロフルオロカーボン類(HFCs): 冷媒、発泡剤、洗浄剤などに使用。フロン類の一種。
- パーフルオロカーボン類(PFCs): 半導体製造、アルミニウム製造などに使用。
- 六フッ化硫黄(SF6): 電気の絶縁体などに使用。
- 三フッ化窒素(NF3): 半導体・液晶製造などに使用。
これらのガスは、大気中濃度、寿命、地球温暖化係数(Global Warming Potential: GWP)がそれぞれ異なりますが、いずれも地球温暖化に影響を与えます。温対法はこれらを包括的に管理することで、日本全体のGHG排出量を効果的に削減しようとしています。
温対法の核:企業に課される「排出量算定・報告・公表義務」
「知る」ことが「減らす」ことの第一歩
温対法に基づく最も具体的かつ広範な企業の義務が、**「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」**です。「企業に排出量の報告義務」とは、まさにこの制度を指します。
この制度は、一定規模以上の温室効果ガスを排出する**事業者(特定事業所排出者や特定輸送排出者など)**に対して、自らの事業活動に伴うGHG排出量を算定し、国(主に環境省、事業によっては経済産業省等と連携)に報告することを義務付けるものです(出典:環境省ウェブサイト『温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度』)。
具体的には、以下の排出量が報告の対象となります。
- スコープ1(直接排出): 事業所内での燃料の燃焼(工場、オフィスビルなど)や、工業プロセスからの排出など。
- スコープ2(間接排出): 他社から供給された電気や熱の使用に伴う排出。
(※SSBJ基準で求められる「スコープ3」は、温対法の報告義務の直接の対象ではありませんが、温対法に基づいて報告されたスコープ1, 2のデータは、企業やそのサプライヤーがスコープ3の一部を算定する際の基礎データとして活用されることがあります。SSBJ基準については、前回のコラム「【SSBJ】サステナ開示の国内基準策定 スコープ3も義務」で詳しく解説しています。)
この排出量報告義務の意義は非常に大きいものです。
- 正確な排出量把握の基盤: 国や地方自治体が日本のGHG排出インベントリ(排出量の目録)を作成し、温暖化対策の進捗を正確に把握するための基礎データとなります(参照:環境省 国立環境研究所『日本の排出量インベントリ』)。
- 企業の排出量認識の促進: 事業者は、自社の事業活動がどの程度のGHGを排出しているかを具体的に算定することで、問題意識を高め、削減の必要性を認識するようになります。
- 削減目標設定の出発点: 現状の排出量データは、企業が自主的な削減目標(例:SBTiで認定される目標)を設定する上での重要なベースライン情報となります。
- 効果的な政策立案への活用: 国は報告された排出量データを分析し、産業部門ごとの排出傾向や削減ポテンシャルなどを把握することで、より効果的かつ効率的な温暖化対策政策(例:補助金の重点配分、規制強化の検討など)を立案・実施することができます。
- 情報公開による透明性の向上: 報告されたデータは、国のウェブサイト(国立環境研究所の集計システムなど)を通じて一般に公表されます。これにより、企業の排出状況の透明性が高まり、企業間の排出削減努力を比較検討したり、投資家や消費者などが企業の環境負荷を評価したりすることが可能になります(出典:環境省 国立環境研究所『温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度』ウェブサイト)。
このように、温対法に基づく排出量報告制度は、単なる事務手続きではなく、「知る」ことを通じて企業や社会全体の温暖化対策への意識と行動を促す、極めて戦略的な仕組みと言えます。
温対法に基づくその他の主要な施策:報告義務だけではない法律の広がり
温対法は、排出量報告義務以外にも、カーボンニュートラル社会の実現に向けた様々な施策の根拠となっています。
- 政府、地方公共団体、事業者の「実行計画」策定: 温対法は、国全体、地方公共団体、そして一定規模以上の事業者に対して、GHG排出量の削減などに関する計画(実行計画)の策定・公表を求めています。これにより、各主体が具体的な目標と取り組みを定め、計画的に温暖化対策を推進することが促されます。
- 国民の努力の促進: 温対法は、国民一人ひとりが日常生活におけるGHG排出削減に取り組むことの重要性を謳い、「国民運動」として温暖化対策を推進するための啓発活動や情報提供に関する国の責務などを定めています。「クールビズ」や「ウォームビズ」といった国民的な取り組みも、こうした法律の理念に基づいています。
- 地球温暖化対策に関する情報の整備と提供: 温対法は、温暖化の現状、予測、影響、対策に関する情報を収集・整理し、広く国民に提供することの重要性も定めています。国立環境研究所などが担うGHG排出量インベントリの作成や、温暖化に関する調査研究なども、この法律の精神に則ったものです。
温対法は、排出量報告制度という「排出量の見える化」を基盤としつつ、計画策定、国民運動、情報提供といった多角的なアプローチを通じて、社会全体で温暖化対策に取り組むための法的枠組みを提供しています。
温対法と現代のGX・カーボンニュートラル戦略との連携
日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」目標や、それを実現するための「GX(グリーントランスフォーメーション)」戦略において、温対法はどのような位置づけにあるのでしょうか。
温対法は、これらの高い目標や野心的な戦略を支える**「法的基盤」および「データインフラ」**として機能しています。
- 目標達成に向けたデータ基盤: 温対法に基づく事業者からの排出量報告データは、日本全体のGHG排出量がどのように推移しているかを把握するための最も重要な情報源の一つです。このデータは、国がカーボンニュートラル目標達成に向けた進捗をモニタリングし、必要な政策の調整を行う上で不可欠です。
- GX政策の効果測定: GX投資や新たな規制導入といった政策の効果を評価するためにも、温対法で収集される排出量データが活用されます。例えば、特定の産業へのGX投資が、実際にその産業からの排出量削減にどれだけ貢献したかなどを分析する際に、この報告データが参照されます(参照:経済産業省・環境省 GX関連政策の効果検証資料)。
- 排出量取引制度などへの活用: 将来的に本格導入が検討されている排出量取引制度などにおいても、温対法に基づく排出量算定・報告の仕組みが活用されることが想定されます。排出量取引は、企業が自社の排出量上限内で取引を行う制度であり、正確な排出量把握が制度運営の前提となるからです。
このように、温対法は、1998年の成立以来、日本の温暖化対策の根幹を支え続けており、現在のカーボンニュートラルやGXといったより高次の目標や複雑な戦略を実現するための、必要不可欠な土台として機能しています。
企業が温対法に対応するために必要なこと:義務の理解とデータの活用
温対法に基づく排出量報告義務の対象となる事業者は、その内容を正確に理解し、適切に対応することが法律遵守(コンプライアンス)の観点から不可欠です。
- 対象事業者であるかの確認: まず、自社の事業所が温対法に基づく排出量報告義務の対象となる規模であるかを確認します。エネルギーの使用量や温室効果ガス排出量などが判断基準となります(参照:環境省『温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度』ウェブサイト 報告対象)。
- 算定方法の正確な理解と実施: 温対法では、GHGの種類ごとに詳細な算定方法が定められています。これらのガイドラインを正確に理解し、自社の排出量を適切に算定する必要があります(出典:環境省『温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度』算定方法ガイドライン)。
- 報告書の作成と提出: 算定した排出量は、国の定める様式に従って報告書を作成し、電子システム(例えば、環境省の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のシステム)を通じて提出します。提出期限も定められているため、計画的な作業が必要です。
- データ管理体制の構築: 毎年継続して排出量を算定・報告するためには、関連するデータ(例:燃料の使用量、電気の使用量、生産量など)を効率的に収集・管理するための社内体制やシステムを整備することが望ましいでしょう。
そして、単に報告義務を果たすだけでなく、報告のために算定した排出量データを積極的に自社の温暖化対策に活用することが重要です。このデータは、自社の排出量の「健康診断結果」のようなものです。
- 排出量が多い部門やプロセスを特定し、重点的な削減対策を検討する。
- 過去の排出量と比較し、削減努力の成果を評価する。
- 削減目標(SBTなど)を設定する際の根拠とする。
- SSBJ基準に基づく将来的な開示に備え、データ収集・管理の精度を高める。
今後の展望と企業への示唆:温対法の進化と脱炭素経営への連動
温対法は、国内外の情勢変化に合わせて今後も改正される可能性があります。例えば、報告対象となるGHGの種類や事業者の範囲が見直されたり、算定方法がより精緻化されたりすることも考えられます。また、GX推進に伴い導入される新たなカーボンプライシングなどの仕組みとの連携も強化されていくでしょう。
企業にとっては、温対法に基づく排出量報告は、今後ますます重要となる脱炭素経営の出発点であり、必須のプロセスとなります。この報告を通じて自社の排出量を正確に把握し、削減に向けた具体的な行動計画を策定・実行することが、単なる法令遵守を超え、企業価値の向上に繋がります。
透明性の高い排出量情報の開示は、投資家や顧客からの信頼獲得にも寄与します(参照:SSBJ基準、CDP質問書など)。温対法への適切な対応は、SSBJ基準に基づくサステナビリティ開示や、SBTiなどの国際的な目標設定イニシアティブへの参加といった、より高度な脱炭素経営戦略を進める上での強固な基盤となります。
結論:温対法は未来への羅針盤の一部
地球温暖化対策推進法(温対法)は、1998年の成立以来、日本の温暖化対策の根幹を支え続けている法律です。京都議定書を契機に生まれ、パリ協定や2050年カーボンニュートラルといった最新の目標を基本理念に掲げながら、進化を遂げてきました。
特に、特定の事業者に対する温室効果ガス排出量の算定・報告・公表義務は、国全体の排出量把握の土台となると同時に、企業が自らの環境負荷を認識し、削減への行動を起こすための重要な仕組みです。この制度を通じて得られるデータは、政府の政策立案や、企業が自社の脱炭素戦略を策定・実行する上で不可欠な情報源となっています。
企業は、温対法への適切な対応を単なる義務としてではなく、自社の排出量を正確に把握し、削減努力へと繋げるための重要な経営ツールとして捉えるべきです。温対法が提供するデータ基盤は、SSBJ基準に基づくサステナビリティ開示や、GXによる事業変革といった、未来に向けた企業の取り組みを支える羅針盤の一部となるでしょう。
温対法の趣旨を理解し、その要求事項に適切に対応し、そして報告によって得られたデータを積極的に活用していくことこそが、企業がカーボンニュートラル社会の実現に貢献し、持続的な成長を遂げるための確かな一歩となるのです。(温対法に関する詳細な情報、報告対象、算定方法については、環境省のウェブサイトをご確認ください。)
エビデンス・主な情報取得元
- 環境省ウェブサイト: https://www.env.go.jp/ (温対法条文、改正履歴、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の詳細、算定方法ガイドライン、日本の排出量インベントリなど、温対法に関する主要な情報源)
- 環境省 国立環境研究所 ウェブサイト: https://ghg-cv.nies.go.jp/ (温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づく事業者からの報告データの集計・公表システム)
- 経済産業省ウェブサイト(特に資源エネルギー庁関連): https://www.meti.go.jp/ (温対法における経済産業省の役割、排出量報告制度における所管事業に関する情報など)
- 内閣官房ウェブサイト: https://www.cas.go.jp/ (地球温暖化対策推進本部など、温対法を含む日本の地球温暖化対策に関する政府全体の情報)
- パリ協定、京都議定書等に関する情報: 国際連合気候変動枠組み条約事務局(UNFCCC)ウェブサイトや、日本の外務省ウェブサイトなどで参照可能。
※本コラムの内容は、公開時点での温対法および関連制度に関する一般的な理解に基づいています。法改正や制度変更が行われる可能性がありますので、常に最新の公式情報をご確認ください。



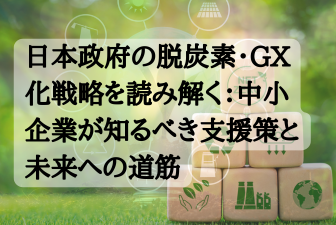
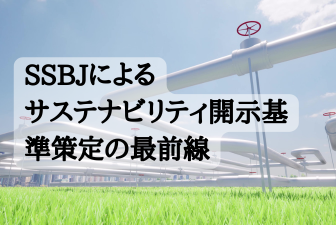





この記事へのコメントはありません。